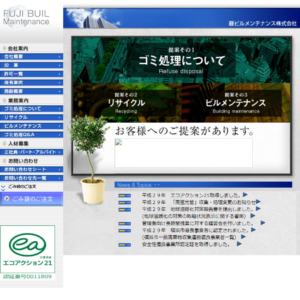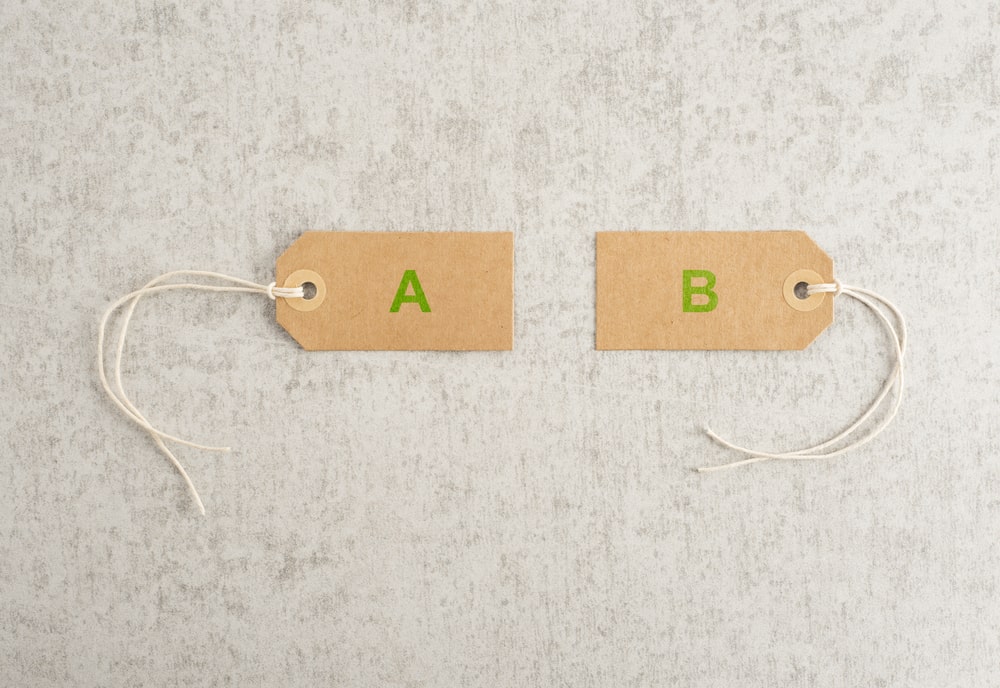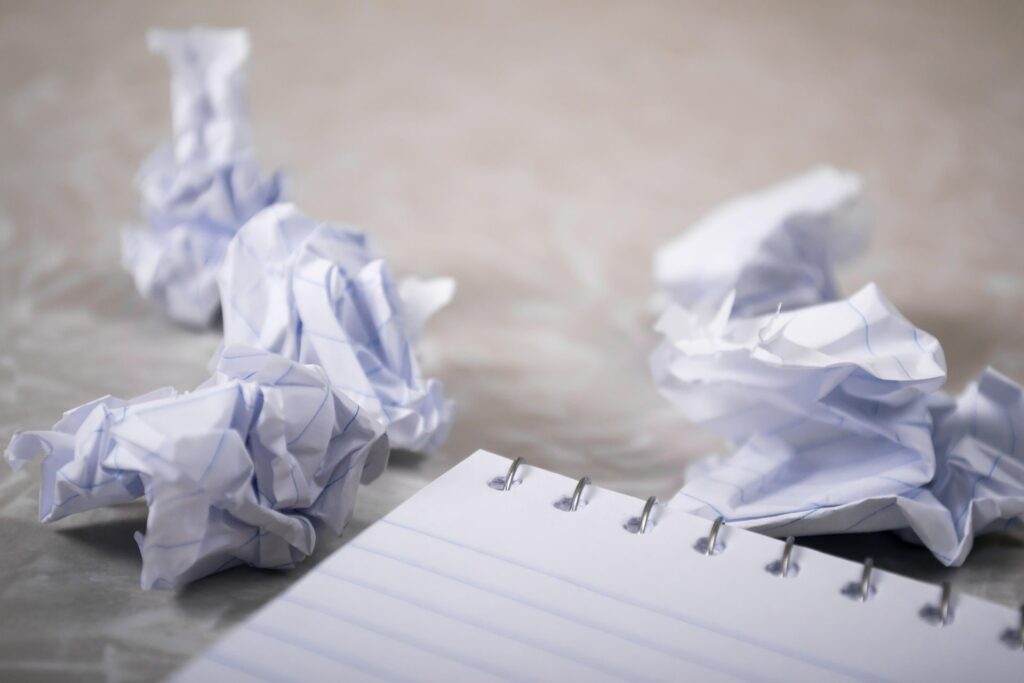知らなかったではすまされない?廃棄物処理の違反で科せられる罰則とは

日常的に出るごみを何気なく処理している方も多いですが、事業としてのごみの扱いには厳格なルールが課されています。事業系の廃棄物については、処理の方法を間違えると法律違反となり、過料や懲役といった重い罰則が科されることも珍しくありません。今回は、廃棄物処理の違反に関する基本的な知識と罰則の内容について紹介します。
廃棄物処理法とは?違反になりやすいポイントを知る
事業者がごみを処理する際に守るべき法律として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」があります。
事業活動に伴って発生するごみを対象とし、その分別、運搬、処分方法などを細かく定めています。
「廃棄物処理法」とはどういう法律?
廃棄物処理法は、廃棄物の適正な処理を目的とした法律で、1970年に制定されました。
ごみの不法投棄や環境汚染を防ぐことを目的としており、処理の責任は原則として「排出事業者」にあります。つまり、企業や店舗から出たごみについては、その出した側が正しい処分の責任を負うということです。たとえ処理業者に依頼していても、不法な処理が行われていた場合には排出側も処罰の対象になる可能性があります。
違反になりやすい行為とは?
よくある違反行為としては、次のようなケースが挙げられます。
・事業系のごみを家庭ごみとして出す
・無許可の業者に廃棄物の運搬・処理を依頼する
・ごみの分別ルールを守らず混合して廃棄する
・産業廃棄物のマニフェストを作成していない
・処理契約書を交わしていないまま回収を依頼する
こうした行為は「うっかり」でも違反となることがあり、罰則の対象になります。
とくに「量が少ないから」「いつも回収されていたから」といった理由で油断してしまうのは危険です。
産業廃棄物と一般廃棄物の違いも要確認
ごみの種類によって、処理のルールや契約先が異なります。
たとえば、オフィスから出る紙くずや段ボールは「事業系一般廃棄物」に分類されますが、機械油や金属くずなどは「産業廃棄物」にあたります。両者を同じ袋に入れて出してしまうと、適正処理ができず違反とみなされるおそれがあります。廃棄物の種類と分類を正しく理解することが、違反防止の第一歩です。
罰則の種類と実際に科せられるケースとは?
廃棄物処理法に違反した場合、行政処分だけでなく、刑事罰が科されることもあります。
どのようなケースで、どのような罰があるのかを見ていきましょう。
不法投棄を行った場合の罰則
最も重い処分が科されるのは、不法投棄です。
自社の敷地内や空き地、公道などに勝手に廃棄物を捨てた場合、個人では「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」法人では「3億円以下の罰金」が科せられる可能性があります。また、不法投棄を繰り返した場合や、組織的に行われた場合にはさらに厳しい処罰が適用されることもあります。
無許可業者への依頼も処罰の対象に
回収業者に処理を任せていても、その業者が必要な許可を持っていなかった場合は、排出事業者も罰則を受ける可能性があります。
無許可の業者に依頼したことで不法投棄が行われた場合、たとえ「知らなかった」としても責任を免れることはできません。許可業者であることを証明する「一般廃棄物収集運搬業許可証」や「産業廃棄物収集運搬業許可証」を事前に確認しておくことが重要です。
マニフェスト未提出にも罰則がある
産業廃棄物の処理では、排出から最終処分までを記録する「マニフェスト(管理票)」の作成と保管が義務付けられています。
この管理を怠ると「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される場合があります。さらに、虚偽記載があった場合やマニフェストを改ざんした場合には、より重い罰則が適用されることもあります。
意外と知られていない「委託契約書不備」のリスク
廃棄物処理を委託する際には、書面による委託契約を交わす必要があります。
口頭での契約や、契約内容が不十分な場合は「契約不履行」とみなされ、行政からの指導や処分を受ける原因になります。適切な処理がなされているかどうかを証明するには、契約書やマニフェストなどの記録が重要な役割を果たします。
違反を防ぐためにできることと適切な対応とは?
廃棄物処理に関する違反を防ぐには、日常業務の中でいくつかの基本を徹底しておくことが大切です。
信頼できる業者と契約する
まずは、正規の許可を持つ信頼できる回収業者と契約することが大前提です。
事業系ごみに関する知識が豊富で、適切な分別や回収スケジュールについてもアドバイスしてくれる業者を選ぶことで、違反リスクを大きく減らせます。インターネットや口コミで情報を集め、実績のある業者を見極めましょう。
社員への教育や分別ルールの共有も重要
実際にごみを扱うのは現場のスタッフであることが多いため、全社員に対して分別ルールや排出のタイミングを周知しておくことも重要です。
事業所内にごみ分別表を掲示したり、定期的にルールを見直したりすることで、現場での誤った処理を防げます。日々の小さな意識が、大きなトラブルを防ぐことにつながります。
処理内容を記録・保存しておく
マニフェストや契約書、請求書などの処理記録は、すべて保管しておくようにしましょう。
行政からの調査が入った際や、万が一トラブルが発生したときに、自社が適切に処理を行っていたことを証明する手段になります。記録の保管期間や書式についても、業者と相談しながら整えておくと安心です。
まとめ
廃棄物処理は、事業を運営する上で欠かせない重要な業務の一つです。法律で定められたルールを守らなければ、罰金や懲役などの重い罰則を受ける可能性があります。たとえ無意識のうちに違反していたとしても「知らなかった」ではすまされません。無許可業者への依頼や、マニフェストの不備、契約書の未締結など、うっかりしてしまいがちなポイントも多く、定期的な見直しや社員教育が欠かせません。確実に法律に沿った処理を行うためには、信頼できる事業系ごみ回収業者に依頼するのがおすすめです。専門業者であれば、適切な処理はもちろん、日々の分別指導や書類管理までサポートしてくれることもあります。安心して事業を継続していくためにも、ごみ処理のルールを正しく理解し、実践していきましょう。

-
 引用元:https://e-bright.jp/
引用元:https://e-bright.jp/